空は晴れ
「ゲルニカ」はいよいよ最終の地、北九州での公演を迎えます。
キャストやスタッフの皆様が、どうぞラストまで無事で駆け抜けられますようお祈りしています。
私が豊橋公演を観劇したときも、気持ちの良い晴天続きでした。
洗濯日和とかお散歩日和など、晴天は一般的に良いイメージ。
しかし戦時には爆撃機から爆弾を落としやすい天候であり、被害を受ける側の一般市民には非常に怖かった記憶のある方もいるのではないかと思います。
誰しも自分の住む土地が一瞬にして焦土と化してしまうなんて悪夢は考えたくないものです。
ゲルニカの地も爆撃の直前まではきっと、いつもの”いいお天気”でいつもの一週間の始まりだったのだろうなあ。。。
サラとマリア
主人公のサラ(上白石萌歌)はゲルニカの領主の娘であり、いとこのテオとの婚礼を直前に控えていた。
トルソーにかけられていた花嫁衣装は真っ白のドレス。
純白のドレスからは、何色にも染まっていない美しさを感じる。
“サラ”もまっさら(真っ新)な印象があり(日本語からだが)、ヘブライ語の名前の由来は”王女”の意味があるそうだ。
まさにゲルニカの”王女”になることを期待されていたかのよう。
でもサラと厳格な母マリア(キムラ緑子)との心の壁は大きかった。
それは新時代と旧時代の大きな隔たりを表しているようにも感じた。
純粋無垢で世間を知らないサラではあるが、差別や偏見には強く母に反発し、決別に至るまでになる。
そんな旧時代に固執し冷徹さが際立ったマリアだが、領主である夫が生きていたころの時代には、もう少し穏やかに暮らしていたものと思う。
夫の死とともに激変してゆく時代の中で、家や血脈を守らねばならないという思いがマリアの心を硬化させたのか。
神に祈りながら背徳を犯したり、ドイツにゲルニカの爆撃を許可したり。神の御心に従おうとすればするほど、出口のない闇へ向かってしまったかのよう。
自身の大きな矛盾にも気がついていたと思うが、迷いや葛藤や哀しみ、愛情すべてを押し込め、独り時代に対峙しようとした人なのだと感じた。
ゲルニカに限らず、歴史の中にもマリアのような人はきっと存在しただろう。劇的な変革の中で現状を守ろうとした方だが、もっと強大な権力の前にあっては一地方の領主の力など、大波に飲まれる木の葉のよう。
マリアは厳格で冷酷な鎧をつけて”家”を守ろうとしたが、最後は自分も望まぬ方向へ向かわざるを得なかったと思う。そんなマリアの背中からはどこか哀しみが漂っていたように思う。
戦争は親子の確執を修復不可能になるまで破壊しつくすものでもあった。
レイチェルについて
マリア曰く、女中のルイサ(石村みか)100人の命よりサラの命のほうが重い、とは今の感覚では明らかに間違いだ。
でもそう昔でもない当時でも、既得権益を持つものの価値観だったのだろうかと思うと、親子とはいえいくら話し合ってもお互い納得する結論には至らないだろう。
国同士ではなおさら。
ゲルニカの中では、もともとの利権を手放したくない勢力 vs それはもう問屋が卸さない「ノーパサラン!」たち。
そんな争いを、それぞれ後方で支援する国々。
支援する国は表向きはいい事言って相手側を悪に貶めるプロパガンダ合戦だから、歴史を把握するのって難しいものだ。
テレビや新聞からの偏光報道の影響もあるし。
今だからこそいろいろと一次ソースを確認したり自分で調べられるようになってきたけれど。
それぞれの勢力で記者を抱え、自分たちに有利な書き方にしてもらうこともある。
そう思うと、レイチェル(早霧せいな)はよくぞ、その正義感に従って実際に行動に移すことができなたと。
内容によっては記事だけでなく記者ごと消される危険性も充分にあったはず。
事実を忠実に書こうとするレイチェルに対し、ドラマチックに記事を仕立て上げるクリフ(勝地涼)は真逆のタイプと言っていい。
しかしどちらもプロパガンダの片棒を担いでいない点では共通している。ポリシーは違えど自分の脚でしっかり歩いているところが共通点か。どこかウマが合うと感じるところがあったのかもしれない。
事実に忠実な記事は人類の未来にとって重要なことだが、いつの時代も事実は簡単に切り取られ、捻じ曲げられやすいもの。
レイチェルのような記者は、当時も現在も非常に貴重な存在であると思わせてくれた。
多面的・多様性
ゲルニカの惨事がピカソの感性であのように描かれたように、事実の記事も書き方で大きく変わる。
受け取る側でも大きく変わってくるだろう。
パンフレットを読んでも思ったが、キャストの皆様も歴史観はさまざまだ。
脚本の長田育恵さんも共感するところが多く作品も本当に素晴らしいと思った。それぞれの登場人物には熱く色濃く、ストーリーを書く上で非常に謙虚である気がする。そうだから自分の脚で歩いてたしかに感じたことを書かれているよう。
事実を書く記者とフィクションを書く脚本家は著すものが違うが、途中のプロセスはレイチェルとも共通するところがあるのかもしれない。
一方で、歴史的な受け取り方で私は共感しかねる点もあった。
(日本軍のことや原爆のことなど。でも反論がこの記事の主旨ではないのでしない。)
しっかり思い出せなくて申し訳ないが、イシドロの食堂でアントニオたちにハビエルがたしか「俺達は静かに侵略されてきたんだ」的なことを言うシーンがあった。
なにもしなければ”戦争”にはならないが一方的に爆撃を受けて国を奪われるか、静かにジワジワ侵略されて奪われてしまうのだなあと。
現在の日本でも領土が危険に晒されている地域がある。やめてくれと言ってもやめない。そんな国が本当にあるからやばい。原因を遡るとアメリカも大きく関係してくるのだが(あ、逸れそう)
多様性多様性と叫ばれる昨今だが、多様性を認めない人たちを認めるのも多様性だとすると、現実的に共存は非常に難しいものがある。
ゲルニカで取り上げられた難民問題は現在の難民問題とも非常に似通っていて、相互理解の難しさや共存の難しさを浮き彫りにしたと思う。
実際難民の映像を見れば「可哀相」と思ってしまう。だが安易な受け入れ(ゲルニカは勝手に流入してしまったが)はその後、別の悲劇をもたらすのだと、ゲルニカの舞台や実際のヨーロッパの事件など目にして痛感した。安っぽい同情心では解決しない難しさを感じた。
一つの事象が他の問題へと発展し、複雑に絡み合って波及してゆくさまを感じさせた一面だった。
暮らし
ゲルニカはピカソからの一方的な視点にならず、多面的な視点を大事にされていることが伝わってきて、いろいろと考えるきっかけになった。
なにより感じたのは、そこには「生活する人」がいたということ。暮らしを描いて人物を色濃く映し出したことは、舞台ならではの力だったと思う。
ちなみに私は過去記事でバスク地方についてさらっと書いたことがあったが、非常に考え方が浅いものだった。
朝夏まなと&咲妃みゆ出演「悠久のアンダルス」(NHK FM 青春アドベンチャー)
書いたときは、遠い昔からそこで暮らしてきた人々の暮らしや文化までは、まったく思い至らず、汗顔の至り。
イグナシオ(中山優馬)が言っていたが、素数は普遍的言語。
全人類、素数でデジタル的に意思疎通できたらもしかしたら争いはぐっと減るのかもしれない。しかしそれは言語も文化もなくなる可能性もあり、民族という概念もなくなりそう。
トルティーヤに舌鼓を打ったり子猫に相好を崩したり。
人が暮せばどこにでもささやかな暮らし、小競り合い、小さな幸せはあるわけで。
そんな人々の熱気を感じさせてもらったなあと。
イシドロの食堂で緊迫した空気になっているときにサラは突然樫の木へ行こうとするシーンがあった。
ゲルニカの地では民衆は皆昔から1000年の樫の木の下で議論を交わし物事を決めてきたという。
どんな時もゲルニカの人々にとって拠り所であり、1000年の生命の前では謙虚にならざるを得ない存在感があったのだろうか。
私も神社や屋久島の杉で感じたが、木には不思議な力があると思う。
きっとゲルニカの木もゲルニカの人々にとっての幹であり根であり不思議な求心力を持っているのだろう。ずっとゲルニカの民の暮らしをそっと静かに見守ってきたのだろうな。
そんな「ゲルニカ」の地名はバスク語で「聖なる樫」を意味するそう。ゲルニカそのものだったんだ。
繋がる命
ラストの爆撃のシーンは非常に大きな音と閃光で、数十秒もないぐらいだが非常に長く感じられたシーンだった。
演出だし安全だとわかっているからいいものの、本物の爆撃はどれほどのものだったか。
そして本来真っ白なウエディングドレスを着て街中の人々からお祝いされるはずのサラは、簡素な服を真っ赤に染めて倒れている。おくるみごと。
弱い存在は一瞬で彼らの色に染められてしまうのだとゾッとした。
それでもサラが命を賭して守った、希望の名を持つ赤ちゃんの命は助かっていたかもしれない。
レイチェルがその場に現れたのも運命的である。
おくるみの中のエスペランツァを愛おしそうに抱く姿は一縷の希望の光を感じた。
戦場記者としての使命はクリフに託し、レイチェルは人間としてあるべき行動を取ったのだと思う。
ストーリーの前半、サラが「子牛はどのように死んだの?産声は上げた?オスなの?メスなの?」などと婚約相手のテオに矢継ぎ早に問うところがあった。
知らぬ間に命が潰えた子牛。イグナシオとテオが遭遇し、銃撃になったときに流れ弾に当たって倒れた馬。(牛だったかも?)
難民に襲われいつのまにかただの”肉塊”になってしまった命。
それらの命は非常に軽く扱われてしまった。
しかしそんな中、レイチェルはエスペランツァを抱き上げることにより、サラに報いることができたと思う。
サラが花嫁になる日を迎えようとする日に、名残惜しんで女中のルイサに母に代わるぬくもりを求めたシーンがあった。子にとって母のぬくもりはなによりも温かく安心するものだ。
サラは爆撃に斃(たお)れてしまったが、死しても赤子を決して地に落とさなかったことは彼女の母としての信念であったかもしれない。
レイチェルはサラが身ごもっていることを察知したとき、不安を口にする彼女に優しく力強く尋ねるシーンが印象的だった。
「サラは、どうしたい?」
「…私…産みたい!」
(※記憶が曖昧の為ニュアンスです。)
自分の意志を言葉に出すことにより責任が生まれるし、自分が決めたことだから納得して進むことができる。
一方的に「母親になるんだからそんなんじゃだめだよ!しっかりしなきゃ!」とかではではなく、
サラに母としての自覚と覚悟を持たせることができたレイチェルの投げかけはとても素晴らしく、心に残るものだった。
おわりに
赤ちゃんは何ものにも染まっていない非常にニュートラルな存在です。
サラの赤ちゃんがその後たくさんの愛を受けて、彩り豊かに自分の人生を歩めたのならば嬉しいです。
爆撃の悲劇にすべてを染められてしまうのではなく、1000年続いてきたゲルニカの木のように、ゲルニカの民が大切にしてきたものは潰えることなく続いてゆくのでしょう。
たとえ黒焦げになろうとも、その木の寿命が尽きても、その後を継いだゲルニカの木が現存するように、絶望と思える中にも何かは繋がってゆく可能性を感じたし、ゲルニカの皆様を思いながらその大切さに思いを馳せました。
扱う題材は重いものでしたが、むしろ暮らしや希望などさまざまな光を感じることができ、また明日に向かって進む活力を得られた観劇になりました。
個人的には早霧せいなさんご出演作品で豊橋公演があったおかげで心に残る良い作品に出会えました。感謝です!
長くなりましたがお読み頂きありがとうございました!

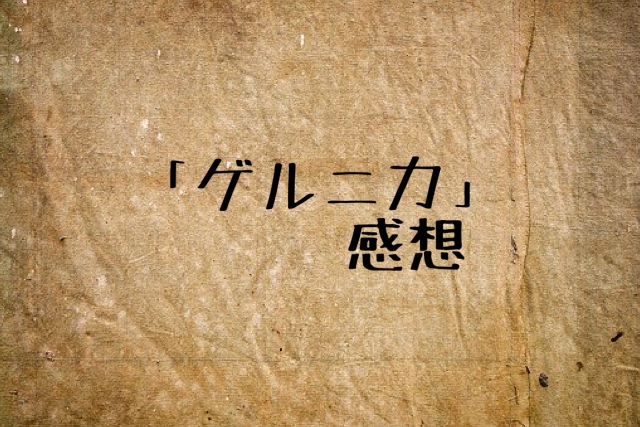














コメントを残す